2021年4月例会

公演

原作:長尾 剛「吾輩はウツである」(PHP研究所)
脚本:瀬戸口郁
演出:西川信廣

明治36年(1903)4月、小泉八雲が辞任したことで学生たちの不満うずまく帝大に、夏目金之助(のちの漱石)が講師として赴任する。不穏な空気の中、学生たちの冷たい視線に晒される金之助は、毎日、不満と苛立ちを抱えながら教壇に立っていた。さらに、失恋で人生をはかなむ学生・藤村操が目の前に現れ、金之助の気持ちはますます不安定になっていく。
そんなとき、一匹の小さな黒猫が夏目家に迷い込む。心が病み始めた金之助は、その黒猫と会話をし始めるが……。
妻と猫と金之助。おかしな三角関係を軸に、不世出の文豪誕生を描くドラマ。

≡≡≡ キャスト ≡≡≡


吾輩
(猫)
今本洋子

夏目鏡子
平塚美穂

夏目金之助
芦田昌太郎
(COME TRUE)

井上哲次郎
(学部長)
小島敏彦

菅 良吉
(講師)
進藤 忠

寺田寅彦
(講師)
小泉真義

てる
(女中)
西海真理

ふさ
(金之助の姉)
まきのかずこ

魚住淳吉
(帝大生)
寺内淳志
(J.CLIP)

小山内薫
(帝大生)
野田 裕

岩波茂雄
(帝大生)
渡辺 聖

安部能成
(帝大生)
村上和彌

藤村 操
(帝大生)
本田玲央

猫③
マツ
木野しのぶ

猫②
シロ
水野千夏

猫①
クロ
小宮山徹



猫+αアンサンブル
長町美幸

猫+αアンサンブル
敦澤穂奈美

猫④
ムサシ
石川惠彩
漱石と舞台と『吾輩は猫である』 原作者 長尾 剛
夏目漱石はウツ病だった。――というのは、事実である。
史実において最終的にその診断を下したのは、日本精神医学界の当時の重鎮・呉秀三だった。そして、それを聞かされた妻の鏡子が、症状を少しでも和らげようとして、寺田寅彦や高浜虚子らに外出の誘いなどを頼み込んでいたのも、事実である。
その一環として、虚子が「気晴らしになれば」と、長文の執筆を漱石に依頼した。そして誕生したのが、漱石のデビュー作にして最高ヒット作の『吾輩は猫である』だった。
だから『吾輩は猫である』は、よく読み込んでみると、猫の飼い主・苦沙弥先生の「中学生相手に本気で喧嘩する」といったような「滑稽ながらも尋常ならざる言動」が、ウツの症状としても、見て取れる。読者は、苦沙弥の言動を笑いながらも、その奥に潜む漱石の「ウツの発散」を感じ取るはずだ。
それはさておき、『吾輩は猫である』の人気ぶりは、相当なものだった。当時は、多くの雑誌や新聞でさまざまな小説が発表されていたが、その中でも『吾輩は猫である』の人気は、群を抜いていた。
そして、とあるプロモーターがその人気に目をつけ、『吾輩は猫である』を舞台化したいと、漱石に働きかけてきた。それが、明治三十九年の九月。『坊ちゃん』『草枕』などを次々発表し、漱石がノリにノッていた頃である。
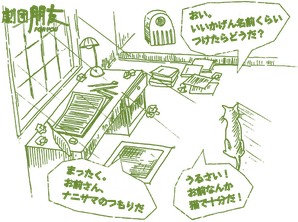
漱石も、この舞台化には、原作者として大いに興味をそそられたらしい。許諾を求めて訪れたプロモーターに、即OKを出した。
その時の状況を、漱石は虚子に宛てた手紙の中で、こんなふうに報告している。
「猫が芝居になろうとは思わなかった。上下二幕とはどこをする気だろう。僕に相談すれば、教えてやるのに」(九月十三日付)
ここで面白いのは、漱石が舞台の演出に興味を持っており、この芝居に自分も一枚噛みたがっている心情が、読み取れることである。
じつは漱石は、英国留学の際に、決して潤沢とは言えない留学費用から色々と算段して、いくつもの舞台を見物している。漱石としては「英国仕込の舞台センス」を発揮したいといった気持ちが、あったのだろう。
もしかしたら漱石は、この『吾輩はウツである』の舞台も「僕も関わりたかったのに……」といったヤッカミを少々覚えながら、天から観ているのかもしれない。
|
会場 日程 |
|
広島市民劇場 |
|
安佐南市民劇場 |
||
|
_ |
アステールプラザ(大) |
|
安佐南区民文化センター_ |
|||
|
|
4月13日(火) |
4月14日(水) |
|
4月20日(火) |
4月21日(水) |
|
|
昼 |
|
- |
13:00 |
|
- |
13:00 |
|
夜 |
|
18:30 |
- |
|
18:30 |
- |
希望日締切 座席シール発行
後援:広島市・広島市教育委員会
